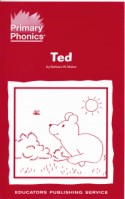イギリスで、2010年に刊行された学校白書”The Importance of Teaching”に記載されているように、イギリスでは、すべての学校でシンセティックフォニックスを教えるようにし、また、そのためのサポートをしていくようです。
・ホワイトペーパーのホームページはこちら
https://www.education.gov.uk/publications/standard/publicationdetail/page1/CM%207980
実際にシンセティックフォニックスについて、どのように記載されているか、みていきましょう。
(We will) Ensure that there is support available to every school for the teaching of
systematic synthetic phonics, as the best method for teaching reading.
(意訳:読む力を教えるために最良の方法である、体系的なシンセティックフォニックスを学校で教えるためのサポートをします。)
the teaching of systematic synthetic phonics as the proven the best way to teach early reading, and the management of poor behaviour in the classroom.
(体系的なシンセティックフォニックスは、読む力を教えるための、また学校で遅れ気味の子どもをのための、いちばんの良い方法であることが証明されました)
として、シンセティックフォニックスを採用することが明らかにされています。
ここで疑問なのが、「なぜ今頃」改革されるの?という点です。
私も、そんなにシンセティックフォニックスが有効なら、どうしてももっと早くの段階で導入されなかったんだろう・・・と思いました。
これは、たぶんsight wordsの呪縛から逃れられなかったんだと思います。
元々英語については、「レターサウンド化できるか」どうかについて大いに議論があったようです。
そこで、重要な単語についてはlook-and-say、見てわかるようにする(sight words)という教育がずっと行われていたようです。
あとは、pot, hotなど単語の一部が似ていることをとらえて文字と音を結びつけるword familyという勉強の仕方もありました。
ただ両方とも単語の記憶力がものをいう方法のため、文字を読めない子どもたちをおいてけぼりにしてしまう・・・ことになっていたようです。今回のホワイトペーパーを見ると、「誰でも」読む力を早期につけるようにする、ことに力点がおかれている気がします。そして、そのための最良の方法がシンセティックフォニックスだった、と思われます。
 Jolly PhonicsのDVDには、アメリカ発音のレターサウンドの発音があるのですが、それがどのような音で、どのように発音するかははっきり説明されていません(もともと発音はできますもんね)。けれども、日本の子どもにとっては、レターサウンドの勉強=発音の勉強になってしまいます。
Jolly PhonicsのDVDには、アメリカ発音のレターサウンドの発音があるのですが、それがどのような音で、どのように発音するかははっきり説明されていません(もともと発音はできますもんね)。けれども、日本の子どもにとっては、レターサウンドの勉強=発音の勉強になってしまいます。